
鶏むね肉のプリン体について食べ方・特徴あわせて解説
2022/07/05追記
※鶏胸肉とプリン体・痛風についての項目にて脱字がございましたため、修正をいたしました。訂正し、深くお詫び申し上げます。
プリン体とは、人間の運動や内臓が働くためのエネルギー源となるものです。体内で生成され続けるほか、動物性、植物性を問わずほとんどの食材に含まれています。
“痛風の原因”として有名なこと、“○〇%プリン体オフ”と謳うアルコール飲料も存在することからあまり良いイメージがないかもしれませんが、プリン体は生命機能の維持に必要不可欠なものです。
そんなプリン体を特に多く含む食品のひとつに鶏胸肉があります。こちらの記事ではプリン体と尿酸・痛風について、鶏胸肉とプリン体・痛風について、痛風時に鶏胸肉を食べる際の注意する点について、それぞれ解説させていただきます。
一般的にヘルシーなイメージのある鶏胸肉ですが、プリン体に注目すると抑えておくべきポイントがあります。この記事を通して、鶏胸肉に含まれるプリン体と痛風の関係について正しい知識を得るきっかけになればと思います。
プリン体と尿酸・痛風について
生命機能の維持に必要なプリン体は食品から摂取するだけでなく毎日体内でも生成されます。体内のプリン体は主に肝臓で分解されると尿酸となり、尿や便として体外に排出されることで体内の尿酸値は一定に保たれています。尿酸は一定量までは血液中に溶けますが排出可能な量を超えると結晶化が進んでしまうため、その結晶が血管を傷つけることから高血圧に、腎臓にたまることで腎不全に、尿路にたまることで尿路結石に、間接にたまることで痛風の原因になってしまいます。
腎不全が起こることによりプリン体を分解する機能が低下し、尿酸として排出しにくく体内に蓄積しやすくなります。腎臓は尿を作る器官であり尿管、膀胱、尿道と尿路に続く道にでもあるため、ここに結晶化した尿酸がたまり出来てしまう結石は激しい痛みを伴います。
“風が吹くだけで痛い”と言われることが由来である痛風は、関節にたまっている結晶化した尿酸が運動などをきっかけに関節を満たす液の中に剥がれ落ち、それを白血球が異物と認識し反応している状態になります。足の指の付け根、足首、足の甲などの足部に起きることが多く、激しい痛みや熱を持った腫れなどが症状として挙げられ、前日までなにもなく突然症状が現れるのも特徴です。1.2週間で痛みはおさまることが多いので治ると前の生活に戻る人が多いですが、血液の高尿酸値が原因のため、生活習慣を改善しないと再発する可能性は高くなります。
鶏胸肉とプリン体・痛風について
鶏胸肉や鶏ささみは低脂肪、高タンパク、低カロリーに加えてコレステロールも低いため、ダイエット中や筋肉トレーニング中に用いる方も少なくありません。ヘルシーな食材であることには間違いありませんが、プリン体に注目するとその限りではありません。それぞれ鶏肉100gに対して含まれるプリン体を数値化すると、胸肉100gにはプリン体が約141mg、ささみ100gには約154mgとなり、これは350mlの缶ビール3~4本相当になります。
生命活動の維持に必要なプリン体は人間の体内でも毎日生成されており、その数値は約700mgと言われていますが、通常時であればそれとほぼ同じ量が排泄により体外に排出されるので人間の体内の尿酸値は一定に保たれています。1日のプリン体の摂取目安量は400㎎とされ、鶏胸肉なら大きめのものが1枚分くらいです。これを大幅に上回るプリン体を体外から摂取することで血液中の尿酸値が高くなり溶けきれない分が結晶化、前の項目の通り高血圧、腎不全、痛風を引き起こすきっかけとなります。
これだけ聞くと鶏胸肉に含まれるプリン体が悪い成分に思えますが、問題なのはプリン体が分解された後の血液内の尿酸値が高くなることにあります。肥満、偏った食生活、ストレス、過度な飲酒など、乱れた生活習慣を改善していくことで体内の尿酸が正常に排出され、血液中の尿酸値が高くなりすぎないようにしていくことで鶏胸肉の食べ過ぎによる痛風などのリスクを下げることが出来ます。
痛風時に鶏胸肉を食べる際の注意する点について
痛風時にプリン体が多い鶏胸肉を食べる際には体内の尿酸値をコントロールする必要があるため、抑えておくべきポイントがいくつかあります。
水分を多く摂取する
水分を多く摂取することで尿量が増え、尿酸が排出される機会も増えることで血中の尿酸値を下げることが出来ます。多い量をまとめて一気に飲むとかえって腎臓に負担がかかってしまうため、コップ1杯程度の水をこまめに、1日に1.5~2リットルを目安に飲むことが目安となります。
また緑茶には利尿作用が、無糖のコーヒーには尿酸値を下げる働きがあるため、水分に加えて摂取することも効果的であると言えます。
アルコールを控える
アルコールには体内でプリン体を生成する効果と、腎臓による尿酸の排出を抑制してしまう効果があるため、体内生産量とのバランスが合わず過剰生産の原因となります。また、プリン体が多いことで有名なビールに限らず、アルコール飲料はそれぞれ原材料の植物性プリン体が含まれているため過剰摂取にもつながります。
乳製品を摂取する
尿酸値を下げるためには尿をアルカリ性に近づけることが必要となります。
牛乳やヨーグルトはプリン体が少なくアルカリ性のため尿酸値を下げる効果が期待できます。
アルカリ性の食材を摂取する
野菜、果実、海藻、きのこ類、いも類はアルカリ性の食材になるので、尿をアルカリ性に近づけ尿酸値を下げる効果から鶏胸肉と一緒に摂取することは効果的です。さらに野菜と海藻類に含まれる食物繊維はプリン体の吸収を妨げる働きがあるので有効な食材になります。果実のバナナには尿酸値だけでなくカリウムによる血圧を下げる働きもありますが、同時に糖分も多くなるため1日1本程度でしたら非常に効果的な食材であると言えます。
ビタミンCを多く含む食材を摂取する
野菜、果実、いも類などに多く含まれるビタミンCには利尿作用があるため、尿酸の排出を促すことから効果的な食材であるといえます。水溶性なこととと加熱に弱いことから調理には注意が必要になりますが、いも類のビタミンCはでんぷんに守られていることから壊れにくいのでおすすめです。
茹でる、煮るなどの方法で調理する
プリン体は水溶性のため、茹でる、煮るといった調理法を選ぶことで鶏胸肉自体のプリン体を減らすことが可能となります。茹で汁、煮汁には溶け出したプリン体が含まれているため注意が必要です。
その他の肉類のプリン体量について
前述したように鶏肉には比較的多くのプリン体が含まれています。では、鶏の他の部位はどうなのでしょうか。鶏肉の部位別プリン体量は以下のようになります。
- 鶏レバー(80g):250mg
- 鶏ささみ(80g):123mg
- 鶏ムネ(80g) :113mg
- 鶏手羽(80g) :110mg
- 鶏モモ(80g) :98mg
また、鶏肉以外の肉類が含むプリン体量は以下の通りです。
- 豚ヒレ(80g) :96mg
- 牛モモ(80g) :89mg
- 牛ヒレ(80g) :79mg
- 豚ロース(80g) :73mg
- 牛肩ロース(80g):72mg
- 牛肩バラ(80g) :62mg
- 豚バラ(80g) :61mg
プリン体量だけを見ると、鶏肉よりも牛・豚肉の特定の部位の方が比較的プリン体量が少ないことが分かります。鶏ささみは高たんぱく低カロリーのためトレーニーやアスリートに人気なイメージがありますが、実際に体を絞りたい方たちの間で鶏ささみよりも注目を集めているのが牛ヒレ肉です。これは、牛ヒレ肉がエネルギー・タンパク質・脂質量で鶏ささみとほぼ変わりがないことに加え、プリン体量が鶏ささみよりも低いためです。
痛風の方や日々の食事からプリン体量を抑えたい方は、鶏肉を控えるというよりも、適切な摂取量を守ることと、前章でご紹介した「アルコール以外の水分を多く摂ること」や「アルカリ性食品との食べ合わせ」などのポイントを抑えることが大切です。
まとめ
鶏胸肉や鶏ささみは低脂肪、高タンパク、低カロリーに低コレステロールであるため、ダイエット中や筋肉トレーニング中に用いる方も多いヘルシーな食材であるといえますが、同時にプリン体を多く含む食材になるので注意することが必要です。
とはいえ、鶏胸肉やささみに含まれるプリン体が直接的に痛風などの原因というわけではありません。体内の尿酸の排出がうまくいかなかったり、体内で過剰に尿酸が生成されることで血液中の尿酸値が高くなってしまったりすることが問題であるといえます。
そのため、鶏胸肉やささみを食べる際には尿酸値をコントロールすることが必要であるため、同時に食べる食材に気を遣うこと、アルコールは控えて水分を多く摂取することといったポイントを抑えることが重要です。
プリン体は生命活動の維持に必要な成分のため、人間には欠かすことの出来ないものになります。肥満、偏った食生活、ストレス、過度な飲酒など、乱れた生活習慣を改善していくことで体内の尿酸が正常に排出されるようにし、血液中の尿酸値が高くなりすぎないようにしていきましょう。
topic:
予約の多い人気プラン

初回限定お試しプラン
※このプランではお買い物代行を受け付けておりません。 美味しいのはもちろん和食、洋食、中華、韓国料理、薬膳料理などどのジャンルであっても栄養バランスを考えた作り置き料理を提供させていただきます。 〜メニュー例〜 真タコとアスパラのマリネ 鱈の甘酢餡かけ ブロッコリーとエビのデリ風タルタルサラダ こんがりチーズのグラタン 野菜たっぷりBBQ炒め チキンとキノコのフリカッセ ハーブ香るパリパリチキン たっぷりキノコの煮込みハンバーグ お野菜の薬膳スープ 参鶏湯(サムゲタン)風鶏煮込み 肉野菜ロール 麹漬け唐揚げ ガパオライス 鶏と野菜たっぷり洋風炊き込みご飯 など お客様を第一にご要望に沿ってお作りいたします。 お気軽にご相談ください。 ※公共交通機関での移動のため最寄駅からご自宅が遠い場合サービスをお受けできない場合があります。
3時間
瞳
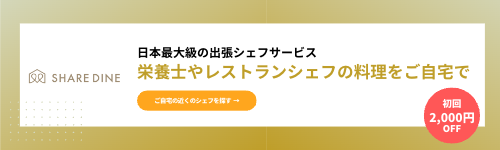
.jpg?auto=compress,format&rect=0,0,1080,1080&w=540&h=540 alt=)



